香港ダムに命を懸けた日本企業ストーリー4
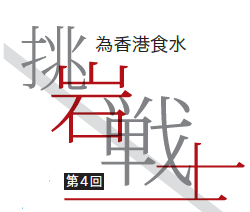 ●前回までのあらすじ〜
●前回までのあらすじ〜
1960代初頭の香港はそれまでに類を見ない大渇水に見舞われた。香港政庁はダムなど貯水施設を建設することを決定し、国際入札に勝ち抜いた日本の建設会社と多くの日本人がこの公共事業に関わり、香港の水不足解消に尽力した。
ダム建設に関わっていた西松建設の機械課長藤沢功氏は、ある日交通事故を目撃した。偶然にもその被害者の叔母は九龍のダンスホールで会った”麗芬“だった。-
あの日以来、藤沢は多忙な業務の暇を見つけては何士傑少年を病院に見舞い、その都度若い叔母の何麗芬とも顔が合った。麗芬から事故を起こした車の持ち主から何の連絡も無いことを聞き、業務で関係のあるアメリカ系保険会社の担当に、当日の事故の模様と車のナンバーを伝えておいた。事故の時車に乗っておらず、叱責を恐れた運転手から事故の報告を受けていなかった車の持ち主が慌てて病院に治療費と見舞金を持って見舞いに来た事を麗芬が電話で報告して来た。その声はもっと明るく弾んでいてもよいのに、弱々しく躊躇いがちであった(何か、あの子の胸に大きな蟠りがあるのだ。あるいは日本人全体に対して・・・)。その後藤沢は暇を見つけては麗芬に自分の戦中戦後の苦しかった生活のことまで打ち明けて、辛い苦しい過去は忘れるしかない、そして明日を考えようではないかと幾度も話し聞かせた。藤沢の心を込めた説得に、氷のように固く冷たく閉ざしていた麗芬の心は段々と溶けて行くようであった。
旧暦の正月の三日、藤沢は麗芬と士傑に映画を見せる約束で九龍で待ち合わせした。元日と二日、普段十分には見られない機械を見回った時、ぬかるみに踏み込み泥だらけになった靴の代わりに、戦後の日本では極く普通だった裏に鉄の鋲の打ってある靴を履いて出かけた。それが明るく晴れた空にカツカツと響き、久し振りに学生時代に戻った気の軽さだった。九龍のホテルの地下のレストランの入り口に立って見渡したが植木が邪魔になって全体が見渡せない。まず左に歩いた、。歩くとまた靴の鋲がカツカツと鳴り響きグリルに木霊した。誰も居ないのでまたカツカツと入り口戻り、カツカツと右の隅に行くとゴムの葉越しに麗芬が見えた。士傑は居なかった。麗芬は蒼ざめて唇を噛みしめ、それが緊張した時の癖である両手を胸の上で固く握り締めて、まるで震えるように。吊上がった目で藤沢を睨むように見た。「そこにいたの・・・」藤沢は笑顔で言って、カツカツと麗芬の前に座った。麗芬は、いまは明らかに身体を震わせて、両腕をテーブルに投げ、その輪の中に頭から埋まって行った。「どうしたの、どこか悪いの?」「何か嫌な事でもあったの?」何を聞いても麗芬は言葉では答えずに、首を振って否定の意思を示した。「さぁ、元気を出しなさい。何か食べようか。」「いらない。わたし・・・もう帰る。」「帰るっ・・・、どこか悪いならお医者さんに連れて行ってあげるよ。」「どこも悪くない。でも気分が悪い・・・私帰る。」麗芬は何かに怯えているように立ち上がった。車で送って行こうと言うのを頑として聞き入れず、はかない影のような姿になって、タクシーでしょんぼり帰って行った。
̶̶そしてそれが、二人がこの世で見ることのできた、お互いの最後の姿となった。
旧正月の休みが終わって、突貫工事が再開された。ダムは次第に形を整えて、低いながらもダムらしい姿を見せ始めてきた。
 そんなある日藤沢は二人の仲を理解している現地スタッフから、麗芬の居る舞庁に行ったら麗芬が居なかった、友達に聞いたらシンガポールに行ったと言われた、と聞かされた。それを聞いて藤沢は驚いた。以前シンガポールに働きに来いと友達から誘われているのだが、と相談された時行かないほうがいいと言い、彼女も行かないと言っていたのに、折角の話し合った結果まで踏みにじられた思いがして、藤沢は不愉快であった。と同時に、あの旧正月の日の彼女の不可解な去り方が、ほろ苦く胸によみがえった。それを伝えた現地スタッフ干少葦は、「̶̶オレ、日本に恩がある。オレ、恩は忘れない。麗芬、日本に恨みあるかもしれない。オレ、オレの受けた恩、麗芬とその家族に返すことで日本に返したい。」と言って麗芬の留守家族を見舞い、どうやらシンガ
そんなある日藤沢は二人の仲を理解している現地スタッフから、麗芬の居る舞庁に行ったら麗芬が居なかった、友達に聞いたらシンガポールに行ったと言われた、と聞かされた。それを聞いて藤沢は驚いた。以前シンガポールに働きに来いと友達から誘われているのだが、と相談された時行かないほうがいいと言い、彼女も行かないと言っていたのに、折角の話し合った結果まで踏みにじられた思いがして、藤沢は不愉快であった。と同時に、あの旧正月の日の彼女の不可解な去り方が、ほろ苦く胸によみがえった。それを伝えた現地スタッフ干少葦は、「̶̶オレ、日本に恩がある。オレ、恩は忘れない。麗芬、日本に恨みあるかもしれない。オレ、オレの受けた恩、麗芬とその家族に返すことで日本に返したい。」と言って麗芬の留守家族を見舞い、どうやらシンガ
ポールから送ってくる金だけで足りないといけないからと、気をつけているらしかった。
そんな干少葦にシンガポールから手紙が来た。「̶̶オレの手紙、サンキューってあったが、たった1枚きり。あんたへの手紙、同封してあったが、厚いよ。こんなに厚いよ。オレ、やけるよ。」冷やかす彼に広東語の麗芬の手紙を日本語に訳して貰った。『香港の母からの手紙で、母や士傑があなたと干少葦さまのご親切でとても安心して暮らし居ることを知りました。あなたの心からのご親切を知りながら、あなたを裏切って逃げてきた私なのに、なんとお礼を言えばいいのでしょうか。でも私はお金や贅沢な暮らしが欲しくてあなたから、香港から去ったのではありません。私はかって、日本人を憎んでいました。西松の人達に遭うまで、日本人の温かい心に触れるまで、ひたすら日本人を憎み続けて育ちました。士傑の事故以来、折角私の心を日本と隔てていた厚い
氷河がほとんど融けてしまっていたのに、あの日、貴方の来られたその「来方」が、またも私の心を、瞬時にして氷河よりも冷たく凍らせたのです。そして私は・・・去ったのでした。』
そして戦争中自分の父と兄は間違って日本兵に殺されたこと。その時自分はまだ幼かった姉の腕の中で、まだどこかに抗日ゲリラがかくれていないかと中庭を歩く日本兵のカツカツという足音に怯えて両手を胸で握り締めて震えていたこと、が細かく説明してあった(そうだったのか。可哀そうな麗芬。・・・俺はそれとも知らないで・・・不注意に・・・なんと残酷な・・・)。藤沢は、不注意にもあの靴を履いて行った、あの日の自分の軽率さを心から悔いた。身体が震えて止まらない。
最終回は6月5日号に掲載予定




 お得なクーポン満載のPPW公式LINE友だち登録はこちらから!
お得なクーポン満載のPPW公式LINE友だち登録はこちらから! ぽけっとページウィークリーバックナンバー No.903
ぽけっとページウィークリーバックナンバー No.903